山形県建築プロデュースPAO
夢、こだわりの実現に向けて住宅に関する無料のアドバイスを行なっております。あなたらしい快適な住まいのご提案PAO
重文 旧尾形家住宅
突然に懐かしい方からの電話がなった。日塔先生からだった。明日上山に入って明後日、以前技師として修復にあたった尾形家を調査で行くが、その前に空いた時間で見たい事例があるから確認してほしい。見たいので、とのとこだった。その願いは叶わなかったかったが、チャンスとばかりに私は尾形家の同行を申し出た。こちらの願いが叶い、国指定重要文化財 旧尾形家住宅の敷地に久々に入る。市の資料には、「寄棟づくりで建坪323m2母屋の桁行26.36m、梁間方向9.61m、上層の農民の大型住宅で17世紀の建築。間取りや座敷に家の格式が示されている。」といかにもそっけなく書かれている。私が興味を持ってもう1度見たいと思ったのは、曲がり柱をうまく壮大は土間空間と藁式を敷き詰めた場所の記憶を呼び戻してのことであった。しかし建物に近づき最初に目にとまったのは、殆ど全ての柱の根本に施された修復の継手の技法だった。早速、日塔先生に質問してみた。「これはその修復完成時の昭和50年の時に行ったものですか。」と。答えが「yes」だった。「私が未だ20代の頃ですよ。部分解体の修復で大変だったんですよ。建物の寄りを戻そうと力を加えて試してみるが、いつのまにか戻っている。」全解体修復ならもっと楽に寄りを戻せたといかにも言いたそうであった。この継手は長年の風雨で腐食した柱を修復する技法で以前にお寺の山門の柱(確か専称寺)に施されたのを見ただけだった。次に目を惹いたのは、内側に煽られた蔀戸だった。市内中心商店街の長い時を経てある店入り口の調査をしてたおかげで、蔀戸という開閉方式はすでにインプットされていた。しかし、このような跳ね上げ方式の蔀戸はどこかの時代劇で見ただけだった。つぎはダイナミックな土間空間だった。自然木の皮を剝いただけのような柱が独立柱で林立する。土のカマドもそのまま残る。黒光りする柱はウルシなのだという。当時は漆文化も盛んで、漆の木も容易に手に入れることができたのだろうといった談義になった。土間から上がった藁敷きのある広間は間口10間(内寸9,504)奥行4間(内寸7,577)で棟丸太下端で8,030もある大空間だ。そこの開口に蔀戸が存在す。そこに華奢は梁が空中で交差する。他にいらした先生は「古い時代の建物程、梁が細い」と。その言葉に妙に納得した。その後、上段の間、次の間と拝見する。そこだけは天井は杉板と竿縁のイナゴ天井だった。そこはやはり、家人が使うことのない空間で、次の間の手前の部屋に式台(貴人の玄関)がついていた。嘗ては突き当りに貴人用内便所が存在したらしいことは、明治時代に書かれた家相用に間取り図で確認することができた。いずれ、さらに詳しいことはスケッチを添えて報告する日がくるであろう。(これ以上のレポートは書けるのだろうか?)

















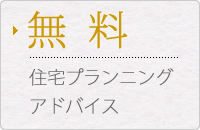
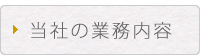

コメントを残す